デジタル変革の波が世界中の産業構造を塗り替える中、日本企業もまた、その歴史上最大級の挑戦に直面しています。書籍『大企業で進むDX』で提示された具体的なデータと事例は、この変革がもはや抽象的な概念ではなく、具体的な数値目標と製品戦略を伴う経営課題であることを明確に示しています。本稿では、資料に記載された数値を一つ残らず引用し、日本を代表する企業が歩むDXの道のりを克明に描き出します。
迫り来る脅威の数値化:デジタル・ディスラプションの客観的インパクト
変革の狼煙を上げたのは、アメリカのウーバー・テクノロジーズが運営する「Uber Eats」のようなデジタル・ディスラプターです。彼らは既存の業界ルールをテクノロジーで覆し、市場を根底から変えました。この脅威に対し、日本企業の危機感は、具体的な調査データとして明確に表れています。
書籍『DX実行戦略』で引用された調査によれば、デジタル・ディスラプションの到来について「市場に大きな変化がすでに起きている」と回答した企業の割合は、2015年の15%から2017年には49%へと劇的に増加。逆に、「変化が起きるのは今後3年以内、およびそれよりも後だ」という回答は、同期間で85%からわずか5%へと激減しました。
自社業界へのインパクトに関する認識も先鋭化しています。「破壊的インパクト」があるとの回答は、かつての**0.4%から約33%へと跳ね上がり、「影響大」は約20%から約44%へと倍増しました。一方で、「影響がないか、あるいは影響小」という楽観的な見方は約26%から約4%**にまで縮小。今や、経営層の7割以上が、この変革を無視できない脅威として捉えているのです。
しかし、この危機感が必ずしも具体的な行動に結びついていないのが実情です。2019年6月にデジタルビジネス・イノベーションセンター(DBIC)がメンバー企業の経営幹部124名を対象に行ったアンケート調査では、実に63%が「デジタル・ディスラプションが自社に与える影響は大きい」と回答したにもかかわらず、54%が「大多数のリーダー層は脅威に気づいているが、適切に対処できていない」と答えました。そして、「積極的に対応している」と断言できたのは、わずか1%に過ぎなかったのです。この「認識と行動の巨大なギャップ」こそ、多くの日本企業が直面する本質的な課題です。
DXを阻む3つの壁:なぜ行動に移せないのか
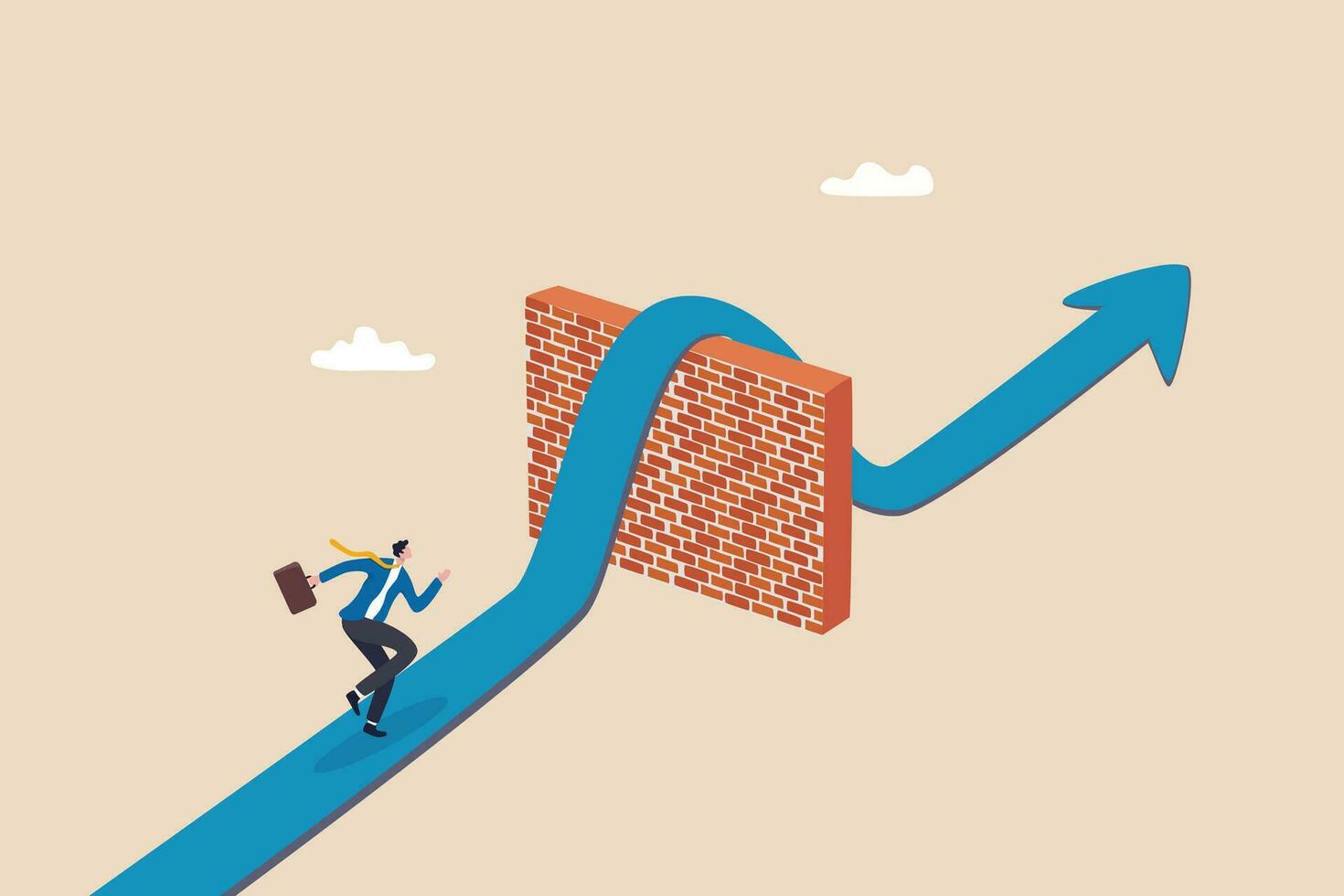
このギャップを生む背景には、DBICの副代表である西野弘氏と、スイスのビジネススクールIMDの北東アジア代表である高津尚志氏が指摘する、日本企業特有の3つの構造的な問題が存在します。
-
強力な「タテ構造」
-
「組織人のメンタリティ」
-
「ソフトウェアの価値に対する理解」の低さ
これらの壁が、クレイトン・クリステンセンの名著『イノベーションのジレンマ』で述べられているような、大企業が変革に踏み出せない状況を生み出しているのです。
3つの戦略的方向性:固有名詞と数字で見るDXの最前線
このような困難な状況下でも、先進的な企業は具体的な製品・サービスを武器に成果を上げています。そのアプローチは、大きく3つの戦略に分類できます。
顧客サービスの強化:体験価値の向上

-
ANAホールディングス:アバター遠隔操作ロボットによる新たな旅行体験「ANA AVATAR VISION」、VRで旅先の雰囲気を疑似体験する「ANA VIRTUAL TRIP」、乳幼児向けの「赤ちゃんが泣かない!! ヒコーキ」など、10件以上のデジタル戦略プロジェクトを推進。業務面では2018年1月からRPAを導入しています。
-
JTB:2018年2月に訪日外国人向けアプリ「ジャパン・トリップ・ナビゲーター」をリリース。マイクロソフト社のクラウド「アジュール」を活用し、AI搭載チャットボット「MIKO」がユーザーをサポート。2019年2月には機能を拡充し、47都道府県を約300エリアに分けて網羅しました。
既存事業モデルの再生:中核事業の再発明

-
日本交通:同社が運営するタクシーアプリ「ジャパンタクシー」は、2019年7月時点で月間利用者数38万人、同年8月にはアプリのダウンロード数が800万を超えました。全国938のタクシー事業者、合計6万6500台超の車両と提携。トヨタやKDDI、アクセンチュアと提携したAI配車支援システムは、都内での検証で94%という高い精度で需要予測に成功。試験導入では、ドライバーの売上が前月よりも1日当たり約20%増加するという驚異的な成果を上げています。同社の川鍋一朗社長のリーダーシップが事業を牽引しています。
-
東京ガス:1998年に古いプログラミング言語「PL/I」で構築された、約1100万件の契約・顧客情報を管理する基幹システムの刷新に2017年から着手。新システムではJavaを用い、SOA(サービス指向アーキテクチャ)とAPIを活用。今後10年かけて1100万世帯にスマートガスメーターを普及させる計画です。
全く新しいビジネスモデルの創出:非連続な成長
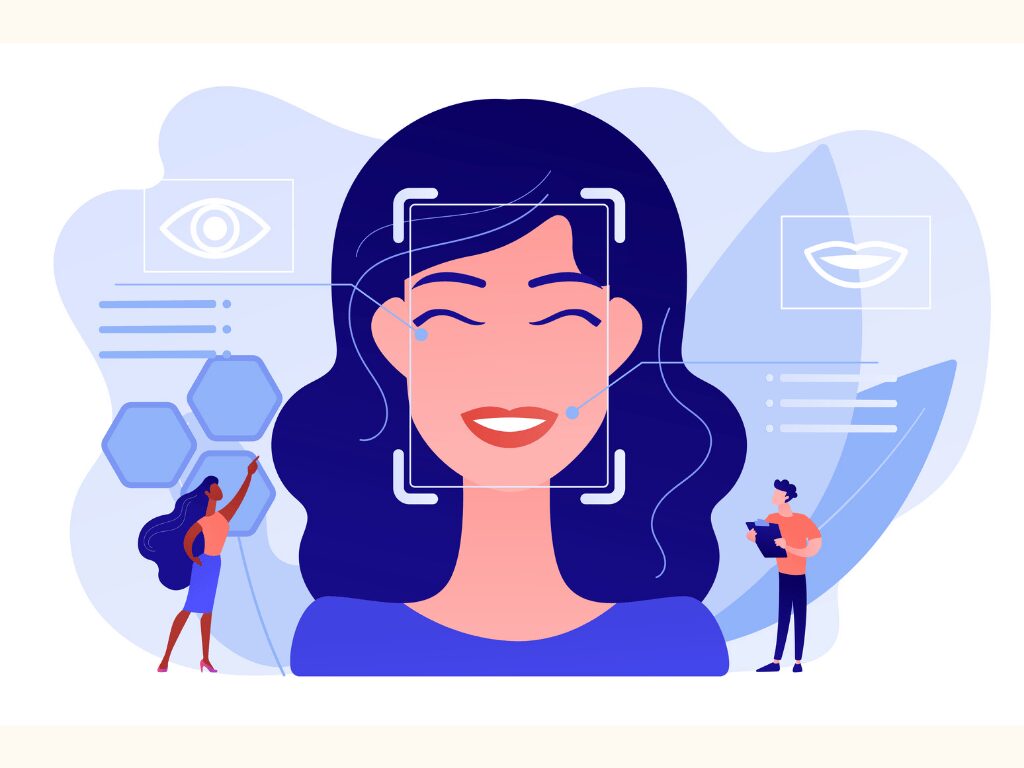
-
資生堂:IoT技術を活用したパーソナライズスキンケアサービス「オプチューン」を月額1万円の定額制で提供。8万以上のアルゴリズムから肌ケアを提案し、専用マシンに搭載された5種類のカートリッジから美容液や乳液が抽出されます。
-
ダイキン工業:三井物産と共同でエアアズアサービス(AaaS)社を設立し、2018年1月から空調空間のサブスクリプションサービスを開始。IoT技術で故障予兆を70%の確率で把握します。この発想は、セオドア・レビット教授の著書『マーケティング発想法』(ダイヤモンド社)の冒頭にある「ドリルを買う人がほしいのは『穴』である」という言葉に根差しています。
-
デンソー:2017年にデジタルイノベーション室を開設。17年10月に米インフィニットキー社を買収、18年1月に米アクティブスケーラー社に出資、同年2月にクリエーションライン(東京都)と米デルファー社に出資、同年4月にオンザロード(愛知県)に出資、19年3月にはエアビクイティ社にトヨタ自動車などと共同出資、19年5月には米ボンドモビリティ社に出資するなど、矢継ぎ早に買収・出資を重ねています。
-
小田急電鉄:2019年10月末からMaaSアプリ「EMot(エモット)」のサービスを開始。タイムズ24(カーシェアリング)、ドコモ・バイクシェア(自転車シェアリング)、日本航空、ジャパンタクシーなどと提携。2019年10月末から翌20年3月10日までの実証実験では、新百合ヶ丘駅の商業施設で2500円以上購入した顧客へのバス無料チケット発行や、新宿駅と新百合ヶ丘駅内のショップで利用できる1日1回500円相当の飲食サブスクリプション30日券を、ほぼ半額の7800円で販売しました。
DX実現への確かな一歩を、NALと共に
本稿で詳述した通り、DXはもはや抽象的な経営課題ではありません。それは、2015年から2017年にかけて「市場の変化」を認識する企業が15%から49%へ急増したというデータに裏付けられた、不可逆的な潮流です。東京ガスが1998年製のPL/Iで構築されたシステム刷新に挑んだように、あるいは日本交通が94%の精度を誇るAI予測で業界を変革したように、その成功の裏には常に高度なソフトウェア技術が存在します。
しかし、経営幹部のわずか1%しか「積極的に対応している」と答えられないのが現実です。この理想と現実のギャップを埋めることこそ、DX成功の鍵となります。
私たちNALは、まさにこのギャップを埋めるための技術パートナーです。アジャイル開発による迅速なプロトタイピング、クラウドネイティブ技術を駆使したスケーラブルなシステム構築、そしてAIやIoT連携による付加価値の高いサービス実現は、私たちの最も得意とするところです。資生堂の「オプチューン」のような革新的なサブスクリプションモデルの具体化、小田急電鉄の「EMot」のようなMaaSプラットフォームの構築、あるいは東京ガスのような大規模な基幹システム刷新まで、貴社のビジネスフェーズに合わせた最適な技術ソリューションを提供します。
NALは、単なる開発会社ではありません。お客様のビジネスに深く寄り添い、課題を共に分析し、最適な技術をもってビジョンを形にする戦略的パートナーです。もし貴社がDX推進において、技術的な専門知識、開発リソース、あるいは新たなアイデアの具体化といった課題をお持ちでしたら、ぜひ一度NALにお声がけください。
AIが観光産業にもたらす革新は始まったばかりです。次の成長の波をどう活用するかが、企業の未来を左右します。
💡 NALは、AIドリブンなデジタルトランスフォーメーションを共に実現し、観光業界の新しい可能性を切り拓くお手伝いをします。
ご関心がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!🚀
👉 ご興味がある方は、ぜひ**こちらのコンタクトフォーム**からお問い合わせください !

